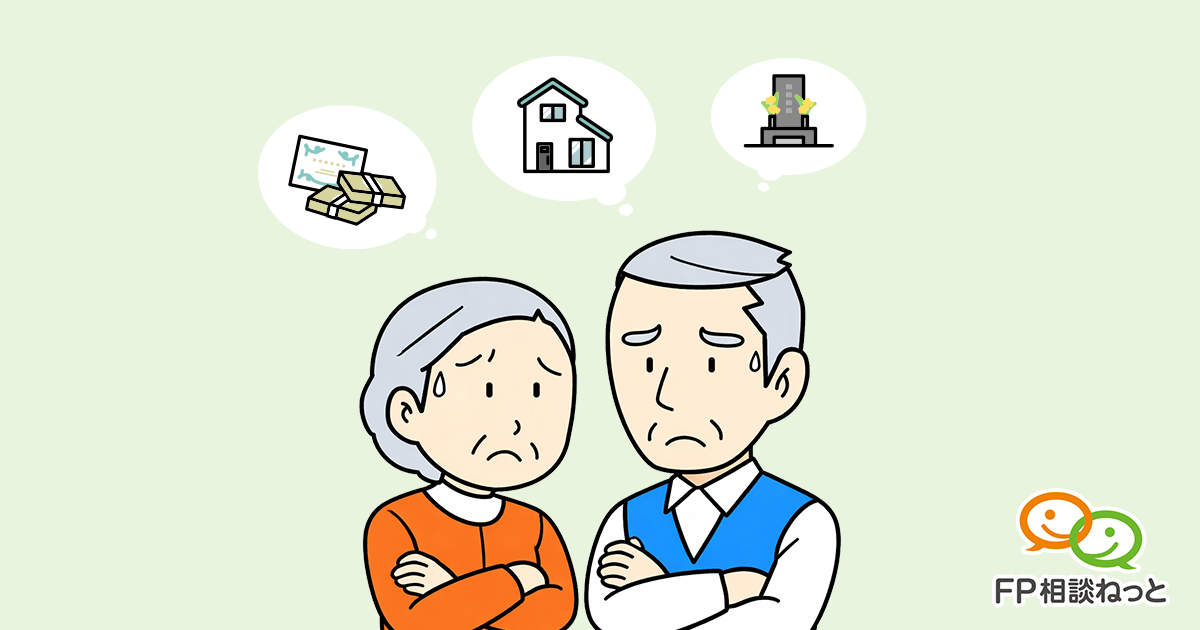ご相談者様DATA
年齢 35歳
職業 専業主婦
性別 女性
家族構成 配偶者(35歳)、子供2名(5歳,3歳)
相談しようと思ったきっかけ
確定拠出年金についてインターネット検索で調べていたら「FP相談ねっと」というサイトを発見し、まずは地元のFP藤方さんに相談しようと思った。
ご相談内容
公的年金だけでは老後の暮らしはなりたたないという話をよく聞きますが、正直今は子どものお金や日々の生活費のやりくりで精一杯。老後資金作りのお金がありません。家計の見直しのポイントを教えてください。
ご相談に対してのご案内
家計を改善する場合の方法は2つ
収入を増やす
支出を減らす
のいずれかになります。収入を増やすことに関しては転職や起業など準備時間が必要になります。まずはすぐに取り組めて効果が期待できるのは支出を減らすことです。ご相談者様にはまず支出を減らすことに取り組んでいただきました。
ステップ1、まずは家計のチェックを
支出を減らすにあたってはまず、月々の収支を把握することからがスタートです。
節約が苦手な方に共通しているのは月々の収支を把握できていないということ。
何にいくら使っているのかがわからないまま過ごし、気づいたら手元のお金が無くなっていたということが多いようです。支出を把握するにはまず家計簿をつけてみることです。買い物のたびにレシート、領収書をとっておき、忘れないようその日のうちに家計簿にメモしておきましょう。家計簿をつけるのがどうしても面倒な方は、スマートフォンで利用できる家計簿アプリを利用しましょう。一目見てわかるグラフや複数の銀行口座残高をアプリ上ですぐ確認できる機能などが充実していて非常に便利です。
きちんと家計簿をつけて把握できたらその次は・・・
ステップ2、支出をグループ分けする
その次は毎月の支出を二つのグループに分けていただきました。
Aグループ
・家賃(住宅ローン返済)
・年金、健康保険料
・民間の生命保険、損害保険の保険料
・車のローン
・駐車場代
・携帯代
・新聞、公共放送受信料、インターネットの利用料
・習い事、お稽古の月謝
・その他会員登録しているサービスの月会費、年会費
Bグループ
・食費
・娯楽費(書籍や楽曲、ゲームなどの購入費、レンタル費用)
・交際費
・旅行代、レジャー費用
・冠婚葬祭費
・その他の雑費
実はAグループとBグループはそれぞれある共通点で分かれています。
さて、それはどういった共通点でしょうか???
正解はAグループ→固定費、Bグループ→変動費という共通点があるということです。
読んで字のまま、固定費は毎月金額が変わらず固定されている。変動費は毎月金額が変動しているタイプの支出です。
この2つのグループに分けたら節約を検討する場合、まず第一に固定費からてこ入れをします。その理由はラクで負担が少ないから。もしBグループの変動費から節約しようとすると、工夫や努力がかなり必要になります。たとえば毎月変動する食費を削るとなると買い物先や献立作りでの工夫が必要ですし、工夫をしても野菜、食材の価格高騰などが発生すればさらに見直しが必要となります。そもそも食べたいものを我慢するというのも長続きさせるのが大変です。交際費などもいつのタイミングでいくら必要になっているかは計算できないことが多いので、節約対象には向いていません。
かたや固定費を一度節約できてしまうと翌月以降特別な工夫や努力は一切必要ありません。何も考えなくて我慢もしなくて良いのでラクです。たとえば車種を買えて車のローン返済額を月々当たり1万円下げることができた場合、1度返済額を下げたらその後ずっとその金額が固定されます。保険料もそう。適正な見直しをして月々5,000円節約できた場合、その後保険料は上がることなくずっと一定となります。
長期的な視点で見ると引越による賃貸家賃の節約も効果が高いです。引越費用こそ一時的にかかるものの、月々仮に3万円節約できた場合、1年間で3万円×12ヶ月=36万円、3年間で108万円が節約できることになります。途中の期間は決められた家賃を払っていくだけで特別な工夫は必要ありません。
また、賃貸マンションから中古の分譲マンションを購入して家賃を節約するという方法もあります。
実際に私のお客様で、以下のようにうまくいった事例があります。
※お客様の事例
【before】
家賃月々10万円
(賃貸マンション3DK 70㎡ 大阪市内 駅徒歩10分)
【after】
住宅ローン返済額+管理費、修繕費合わせて月々7万円 ※35年ローン 変動金利
(中古分譲マンション3LDK 75㎡ 大阪市内 駅徒歩3分)
家賃は月々3万円以上、年間約40万円の節約ができました。ちなみにリノベーション後の引き渡しだった為、以前の部屋と比べ、広く新しいデザインの間取りに仕上げられていました。
現在は住宅ローン金利が非常に低く、頭金0円のフルローンも組みやすく、さらには住宅ローン控除やすまい給付金、利子補給制度(自治体による)等住宅購入者にとってメリットの多い制度がそろっています。こういった住宅購入の追い風を利用して節約を実現するのも非常に有効です。
ステップ3、固定費の見直しとポイント
相談者の方には以下の項目について節約のポイントをご案内致しました。
《通信料》
携帯代、インターネットプロバイダ使用料は節約できる余地のある支出です。携帯電話の契約にインターネットプロバイダのセット契約で見直すと一月あたり数千円の割引が適用されるようなキャンペーンが行われています。そういった情報をこまめに収集し、条件の良いものに見直すと良いでしょう。手続きから2年や3年以内に見直すと中途解約の違約金が発生することもあるので注意です。しかし、最近は中途解約金も含めてキャッシュバックされるキャンペーンも見受けられますので、総合的に比較検討するのをおすすめします。
携帯電話ではインターネット検索時に必要な通信データ量を追加課金方式で増やしていく契約形式もありますが、毎月データ量を多く使用されている方は、課金のないように使い放題プランや、大容量の定額プランを選択されることをおすすめします。
ご相談者の方はご家族で通話、データ通信利用、毎月課金サービスの利用も多かったため
- 通話し放題の定額プランへの変更
- データ通信量定額プランへの変更
- 世帯割引の活用
- 毎月課金サービスの取捨選択
をお勧めしました。
相談者様がすぐにそれぞれの手続きを進められた結果、毎月5,000円の節約が実現しました。
《生命保険料》
生命保険は、ご自身の生活環境や家族環境の変化に応じて契約内容を確認し、必要に応じて見直しましょう。死亡保障、医療保障が今の自分に適正な設定になっているか?過不足はないか?今の公的保険、医療制度に沿っているかどうか?などのポイントを確認してください。内容が把握できていない特約がたくさん付加されていたり、独身の場合、必要以上の死亡保障がつけられていないか?など一度確認してみてください。
ご相談者様の場合、将来計画をじっくり伺った上でライフプランニング表を作成し、人生計画に必要な保障を検討致しました。その結果わかったことは
- 死亡保障は現在時点では不足、9年後以降は逆に過剰になっている
- 医療保障には公的保険制度ふまえると不足している部分と、過剰な特約が付加されている部分とが共存している
- 老後資金目的で加入されている終身保険。しかし、なぜか80歳を過ぎてやっと解約返戻率(支払保険料に対して解約時に受け取ることのできる払戻金)が100%を越える設計になっている
- 教育資金目的で加入している学資保険に必要以上の医療特約が付加されている
という課題が見つかりました。
保障が必要な部分は残し、過剰部分や不必要な保障を削減し、不足部分を目的に見合う保障に切り替えたところ、月々約8,000円の節約が実現しました。
《家賃》
家賃や住宅ローンなども長期の視点で見れば大きな節約につながります。年間の家賃、住宅ローンの返済額合計の目安は年収の25~30%までです。この目安を超える場合は、別の物件へ引越すことで大幅な節約につながります。ご相談者は子どもさんの進学を見据えて引越しを検討しておられました。ご希望エリアがあるようで、ライフプラン表をふまえて賃貸、分譲(新築or中古)のそれぞれメリット、デメリットを情報提供差し上げました。その結果中古分譲マンションのご購入を検討され、ご紹介差し上げた仲介不動産屋で物件が早期に見つかったためにご相談の3ヶ月後には引越が実現しました。元の物件家賃と比べ、月々25,000円以上のローン返済額を抑えることに成功しました。
《自動車費用》
車を所有すると駐車場代、保険料、税金、ガソリン代、車検代等の維持費が必要となります。普通車であれば年間で60万円~100万円かかる計算になります。都心部の公共交通機関の利便性の良い地域にお住まいであれば、車所有の必要性から検討してみてはいかがでしょうか。最近では必要なタイミングだけ利用できるカーシェアサービスを活用される方も増えてきております。また、必要なときだけタクシーを利用するという選択肢のほうが意外と費用は抑えられることも考えられます。
ご相談者様は実際自動車を現在所有はしていますが、乗るのは週末のみとのこと。それもほとんど自転車でも行けるような近場で特に自動車を所有することに優先度は低いかもしれないとのことでした。ご家族でご相談された結果、自動車を下取りに出し、カーシェアリングサービスを利用されることになりました。その結果、月々約35,000円の節約につながりました。
≪節約の結果≫
上記のポイントを踏まえ、今回のご相談者様は
通信料→-5,000円(他キャリアのキャンペーンを利用)
生命保険→-8,320円(必要保障を見極め、スリム化)
家賃→-25,850円(中古分譲マンションへ引越)
自動車の維持費→-35,000円(下取り→カーシェアリングを活用)
合計74,170円の節約に成功し、月々の収支も大幅に改善されました。
節約をする際は今回のご相談者様のように
- 月々収支の見える化、現状把握
- 固定費、変動費のグループ分け
- 固定費の節約
の3ステップで進めてみてください。
節約できた後は・・・
節約に成功し、家計のスリム化がはかれたら、将来の積立にまわせるお金を具体的に決めていきます。まずは積立てる目的に応じたタイミング(①10年以内に使う、②10年超~20年の時点で使う、③20年超の時点で使う)で積立金額を区分する必要があります。ご相談者様の場合、iDeCoへは③の区分で積立てることになります。
- 10年以内に使う
冠婚葬祭、家電の故障、治療費、数年後に確実に必要になる学費等すぐに必要になるか可能性があるお金は普通預金や定期預金で準備しましょう。具体的な使い道が未定の場合、目安とし3ヶ月以上の生活費は最低限貯蓄されておかれると良いでしょう。
- 10年超~20年の時点で使う
10年以上先に必要になる可能性がある、高校、大学の学費、留学費用等の準備は普通預金、定期預金だけでは金利面のメリットがなかなか享受できません。ライフプラン、リスク許容度に応じてNISA(少額投資非課税制度)を活用した投資信託での積立や終身、養老等貯蓄性のある生命保険を活用しての積立が効果的です。
- 20年超の時点で使う
ご相談者様の場合、iDeCoの老齢給付を受ることができる60歳までは25年の時間があるため、この区分での準備となります。
ご相談者様の場合、節約できた月々の収支を全額積立にまわせる状況でした。
ライフプランニングシュミレーションで明確になった資金計画を元に①、②、③の区分で以下のように積立金額を配分しました。(百の位以下切捨て)
- 10年以内に使う→月々24,000 円
- 10年超の時点で使う→月々35,000円
- 20年超の時点で使う(iDeCoで積立てる)→月々15,000円
生活状況に応じて月々の積立額は変動します。今後は状況に応じてその都度ご相談頂きながら積立計画をすすめることになりました。iDeCoは年度に一回まで積立金額変更が可能ですので、状況変化による積立計画変更にも対応しやすい制度と言えます。