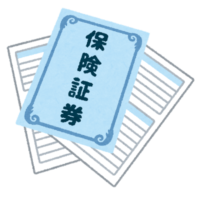こんにちは。
FP相談ねっと認定FP 寺田紀代子です。
青森県弘前市で保険にまつわるお悩みを中心に相談承ってます。

「死亡保険金受取人」生命保険を申込む際、必ず設定するので、皆さんご存知ですよね。
どなたを設定していますか?
「配偶者」パートナーがいる場合、最も多い選択。
「親」パートナーがまだいない場合、この選択も多いですね。
「子」配偶者も親もいるけれど、自分に万一のことがあったら、わずかでも子ども達に財産を残したいんだ!というケースもあります。
指定できる範囲は、保険会社により若干違いますが、原則、配偶者、2親等以内の血族(親、子、祖父母、孫、兄弟姉妹)です。
自分にもしものことがあった時、だれに受取ってほしいか、それぞれ想いはありますが、指定の仕方によって、かかる税金が違います。
お子さんに設定した場合は、成人になるまでお子さんが受取れない、等分に指定したつもりなのに、思った通りに届かないケースもあるようです。
想いが届かないのは悲しいですね。「死亡保険金受取人」は安易に決めてはいけません。
『講談社 現代ビジネス マネー現代』様に掲載させていただきました。
前編 安易に考えてはいけない「保険金の受取人」…「思わぬ税金」がかかってしまう「意外な落とし穴」
後編 「1000万円」がまるまる長女に…死亡保険金を子どもたちに「割合で配分」したはずが、訪れた「思わぬ事態」
誇張しているわけでも、脅かしているわけでもありません。
現場でよくあるご相談をまとめています。
ご覧になってください。