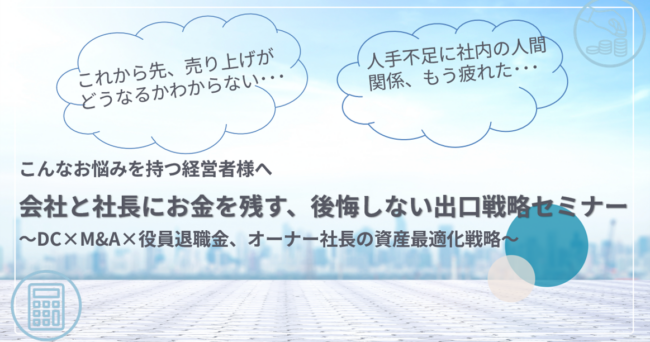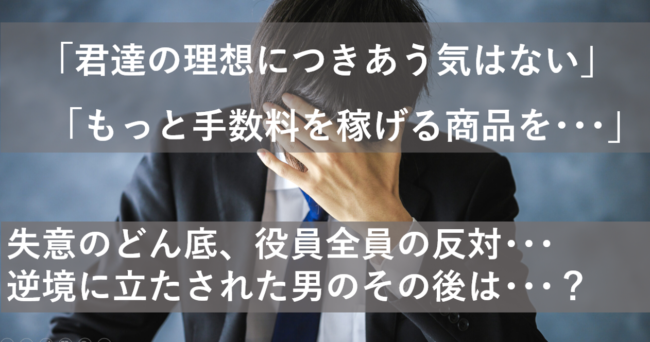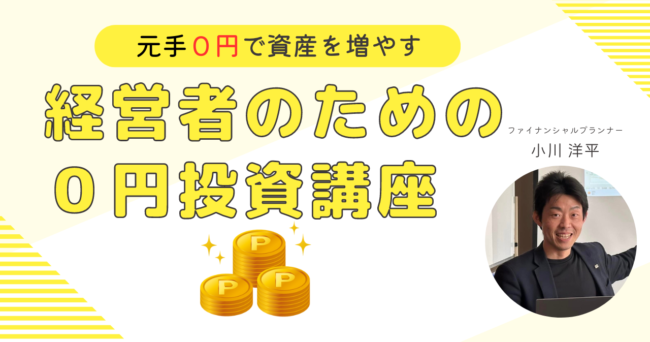変額保険有期型と、NISAでの積立投資+死亡保障を比較し、変額保険はコストがたくさん掛かり資産形成には不向きだという論調がインターネットやYouTube動画では目立ちます。
それはホントなの?実際に同時期に5年間積立をされていた方のデータをもらい、結果を検証してみたいと思います。
※このコラムは一般的な保険商品の考え方、資産形成の考え方について記載したコラムであり、特定の商品の勧誘、販売を目的としたものではありません。
※保険商品の詳細については生命保険会社、募集資格を持つ方からしっかり説明を受け、納得してからご判断されてください。
※保険会社によって商品の仕組や制度の取り扱いが異なる場合があります。
変額保険とは?
「変額保険」と一言で言っても、実はさまざまなタイプがあります。主に以下の3つが一般的に販売されています。
①変額保険(有期型)
②変額保険(終身型)
③変額個人年金保険
また、法人契約では定期型の変額保険が使われることもありますが省きます。今回はその中でも、「変額保険(有期型)」について深掘りしていきますが、その前に、それぞれの特徴をざっと確認しておきましょう。
まず共通しているのは、変額保険は「特別勘定」という、保険会社が用意した投資信託のような運用メニューを契約者が選び、その運用実績によって将来の保険金や満期金、年金額が増えたり減ったりするという点です。元本保証はなく、あくまで投資リスクを契約者が負う商品ですが、そのぶんリターンも期待できるという仕組みになっています。
今回はソニー生命さんのパンフレットから引用させていただきます。
※当該商品を推奨、批評するものではありません
①変額保険(有期型)
変額保険(有期型)は、保障と資産形成がセットになったタイプの保険です。たとえば、契約期間中に死亡や高度障害があれば保険金が支払われ、何もなければ満期時に積立の成果として「満期金」を受け取れる構造です。
最近では、死亡保障だけでなく、要介護状態や所定の障害状態に対する給付が付帯されている商品もあり、万一に備えながら資産形成ができるという特徴があります。
このタイプの保険は、たとえば学資保険の代わりに活用して子どもの進学資金を準備したり、経営者が将来の退職金を兼ねて契約するケース。将来の介護資金の確保のためにも使われています。運用がうまくいけば、支払った保険料を上回る満期金を受け取れる可能性もありますが、逆に運用成績が悪ければ当初予定していた満期金の金額を下回ったり、元本割れとなるリスクもあるため、しっかり内容を理解して契約することが大事です。

www.sonylife.co.jp/examine/lineup/list/pdf/OA09.pdf
②変額保険(終身型)
終身型はその名の通り、一生涯の死亡保障が得られる保険です。運用成績によって死亡保険金額や解約返戻金の金額は変動しますが、契約時に設定した保険金額は確保されるため、相続対策や葬儀費用の備えとして活用されることが多いものです。所定の要介護状態になった場合には死亡保障と同額を生前に受け取れる特約などを付帯できる商品もあります。
一般的に、円建ての終身保険と比較すると変額保険(終身)の方が予定利率が高く設定されていて保険料が安く設定されています。

www.sonylife.co.jp/examine/lineup/list/pdf/OA10.pdf
③変額個人年金保険
個人年金タイプの変額保険は、保障機能はほとんどなく、資産形成にほとんど特化した商品です。保険というよりは、積立投資のための手段として位置づけられることが多く、商品によっては保険関係費がほとんど引かれないタイプもあります。運用結果はどの商品を選んだかによって異なり、一定年齢になったら年金形式で受け取れるほか、解約や減額で一括受け取りも可能です。
NISAを使って投資信託で積立するような場合、もし万が一があった場合には亡くなった人のNISA口座を引き継ぐことができず、遺産分割協議を終えて相続人の自分の証券口座(NISA口座には移せない)に移すことになり手続きが煩雑になりますが、変額個人年金の場合は積立金相当額が死亡保険金として指定した受取人が請求する権利を有するため相続の際には非常にスムーズに財産を承継できるというメリットがあります。
そのため、シニアの方の資産形成、資産運用にはこちらの商品の方がNISAよりも向いているとも言えますね。

www.sonylife.co.jp/examine/lineup/list/pdf/OA107.pdf
と、ここまで解説してきたように、よくネットで酷評されてる変額保険も、ちゃんと目的や場面に合った使い方をすればしっかり役に立ってくれてるものなんですよね。
では、この中でも最も批判の的になりがちな「変額保険(有期型)」について、「ぼったくり説」の検証に入っていきます。
ネットで評されてる「変額保険はぼったくり説」とは?
変額保険は、ネット記事やYouTubeなどでしばしば「手数料ばかり取られるぼったくり商品」として名指しされています。
特に、資産形成を目的とする人々にとっては、つみたてNISAやiDeCoと比較して「コストが高すぎる」と言われる場面が多く見られます。
しかし、そもそも「変額保険」と一口に言っても、前章で解説したように、①有期型、②終身型、③個人年金型とタイプはさまざまです。そして、目的によって選ぶべき商品は異なります。
中でも、変額個人年金保険に関しては、実は保険関係費(いわゆる保障にかかるコスト)がほとんど引かれず、募集人さんの販売手数料も少ないことが一般的です。
私自身もかつて生命保険の募集人として経験がありますが、月額1万円程度の変額個人年金の契約ではほとんどボランティア(某社の商品で好きな商品があったのでそこそこ売ってましたが)、現在も提携している募集人さんに変額個人年金の少額な契約をお願いするときは「手間賃にもならず悪いけど・・・」って思いながら契約をお願いしてます。
ネットで「ぼったくり」と叩かれるのは主に【変額保険(有期型)】です。このタイプは、保障と資産形成がセットになっているため、死亡や高度障害などのリスクに備える保障機能と、その裏での投資運用に対してのコストが組み込まれています。
例えば、ソニー生命さんのパンフレットに記載されている変額保険有期型の保険料や契約内容を見てみましょう。

35歳男性の場合、毎月の保険料は22,300円で、65歳まで30年間積み立て、3.0%で運用した場合に30年後に1,000万円になるというものです。
一方で、同じ積立額を年利3%で運用しながら同じ年数積み立てると、30年後の積立額は300万円も多いという結果になります。

当然、変額保険の保険料には死亡保障等の保険関係費が含まれていますので、単純なリターンは劣りますので、シンプルに比較すると変額保険は不利という結論になります。
では、今度は掛捨てで同額の定期保険を契約した場合で比較してみましょう。
今回はライフネット生命さんの定期保険で試算してみます。

この分の保険料を差し引いて積立額を計算してみましょう。

と、同じ運用利回りで計算すると、保険料分を差し引いてもたしかに定期保険+NISAでの積立の方が有利という結果になりますね。
ただし、ここで見落としがちなのが、保険募集人が契約者に対して投資の知識を丁寧に説明し、リスクとリターンを理解してもらったうえで契約を進めるというプロセスです。これは意外に手間がかかる作業で、私も資産形成の教育、投資先のアセットアロケーション設計、商品の選び方のサポートまで行って、それなりに報酬をいただいております。
自分で商品選んで積立できるならばわざわざ変額保険(有期型)を選んで保障と資産形成をセットにする必要もなく、資産形成はiDeCoやNISAを使い、保障は掛捨てで設定しても良いでしょう。
しかし、両方のニーズがあり、誰かに教えてもらいながら選びたいという人にとってはぼたっくりでもなんでもない「相応のコスト」を払っている商品と言えますね。
ちなみに、中身の特別勘定(投資信託のようなもの)については手数料の安いインデックスファンドとアクティブファンドを選べるものがほとんどで、アクティブファンドについてはネット証券で購入できる商品よりも信託報酬が低めに設定されていることも多くあります。
では、実際に変額保険(有期型)と、つみたてNISA+死亡保障を組み合わせたケースではどちらが得をしたのか、そんな疑問に答えてくれるデータを、実際にFP仲間である保険代理店のM社長が実際に5年間にわたり積み立てを行い、変額保険とNISA+定期保険の運用結果を比較した実録を提供してくれましたので検証してみます。
3.そんなに悪くないんじゃない??
「変額保険はぼったくり」と言われ、上記の試算でも変額保険が不利という結果になっているのですが、実際のところどうなのかを自らの手で検証すべく、2020年から実際に積立を開始したのが、FP仲間の保険代理店を経営するM社長(契約当時42歳)です。
M社長は、変額保険(有期型)と、つみたてNISA+同程度の死亡保障の定期保険を並行して契約し、運用結果を比較。同時期・同額での積立によって「変額保険は本当に損なのか」を体験的に示してくれました。
比較条件は以下のとおりです。
・変額保険(有期型)M生命
毎月25,000円積立。特別勘定は「世界株式型インデックス」。
保障額は12,207,000円。
・つみたてNISA+定期保険
NISA:毎月25,000円を世界株式型インデックスで積立(信託報酬はどちらも0.1%前後)。
定期保険:死亡保険金1,250万円。保険料は月額8,475円(非喫煙・優良体)。
合計積立負担額は毎月33,475円。
契約から55か月後(約4年7か月)時点での運用実績は以下のとおりです。

(ChatGPTで作成した比較表のため名称の正確さはご容赦ください・・・)
この比較では、コストを加味せず純粋な積立資産額においてはNISAが2,005,330円で、変額保険は1,391,878円となっており、掛捨ての分の保険料負担分の466,125円を差し引いた分を考慮すると1,539,205円となり、NISA+定期保険の方が約15万円多くなっています。万が一があったときも、定期保険の保障額+NISAの積立額となりますので、変額保険を上回っていおり、確かに「資産形成+保障」での効率性はNISA側に軍配が上がります。
上記は非喫煙優良体という、保険料が最も安い状態で契約しての試算でしたので、今度は別条件での比較も行いました。
・非喫煙・標準体の場合
保険料:10,150円/月 → 55か月=558,250円
NISA資産から保険料差引後の純資産:1,447,080円
変額保険との差額:約55,000円(NISA側が有利)
・喫煙・優良体の場合
保険料:11,962円/月 → 55か月=657,910円
純資産:1,347,420円
変額保険との差額:約44,000円(変額保険が少し有利)
・喫煙・標準体の場合
保険料:18,950円/月 → 55か月=1,042,250円
純資産:963,080円
変額保険との差額:約43万円(変額保険が大きく有利)
この結果からわかるのは、喫煙者や健康リスクの高い人ほど定期保険の保険料が割高になるため、変額保険が有利になるという点です。逆に、非喫煙で健康状態が良好な人は、NISA+定期保険の方が合理的に感じられるでしょう。
ただし、定期保険+NISAの方が死亡時には死亡保険金+NISAの積立額が戻るためより保障コストは本来こちらの方が掛かるはずという点も考慮すべき点と言えますが、積立額に加えて死亡保険金額を上乗せしてるとそもそも負担が大きく、本来でしたら掛捨ての保険料とNISAでの積立額を揃えて比較する方が正確に比較をできたことでしょうね。
ただ、ここで言えることが、「結局大して変わらんよね」ということです。
結論:「商品に罪は無い」
今回テーマにした変額保険(有期型)は、資産形成の意向しか確認していない人に対して
「世界株式型で増えるんです」
「ドルコスト平均法で積立するから損しにくいんです」
など、あまりに安直で誤解を招くトークで、顧客に対してロクに資産形成の教育もしないまま販売していたり、あろうことか「払済」という途中で保険としての重要な保障の機能をほとんど失ってしまうような手続きを行うことを前提にしてリターンを高く見せようとする悪質な提案を行っている募集人もいて、「保障+資産形成」というそもそもの商品の目的に合わない販売をしているので「ぼったくり」扱いされてしまっています。
しかし、しっかりとしたスキルを持ち、相応の知識の提供を行い、顧客の目的に合った提案をしてくれる人から契約するのであれば「ぼったくり」ではなく「相応の対価」と言えるものでしょう。
また、変額保険には「支払免除特則」があり、三大疾病などで所定の状態に該当した場合には、それ以降の保険料が免除される仕組みがあります。これは、将来病気等で大きく収入が減少した場合でも保険料の支払いはストップされても必要な資産を創ることができるというメリットがあります。
別途掛捨ての保障で三大疾病の保険などで対処することもできるのでこの保険に付帯する必要もありませんが、シンプルに一本化したいという方にはメリットと言えるでしょう。
そして、近年では介護保障や障害状態での生前給付が付帯できるものも多く、死亡保障だけでなく「生きている間の備え」としての機能も強化され、保障の面では売っていない立場の私から見てもかなり優秀な商品になってきています。
緊急時の対応力という点では「契約者貸付」という機能も見逃せません。これは、解約返戻金の一定割合を借り入れられる仕組みで、積立の途中で一時的に資金が必要になった場合の“逃げ道”として活用できます。もちろん利息は発生しますが、解約せずに資金を確保できる点は柔軟な資金設計に役立つでしょうし、経営者さんにとっては役員退職金等の資産形成をしながら投資信託を売却せずとも緊急時の資金調達の手段を残しておくことができます。
「変額保険=損」という0か1かの二元論な判断ではなく、「何のために」「どう使うか」で良し悪しが大きく変わる商品と言えます。
自分でNISAや保険を設計し、運用もメンテナンスもできる人にとっては、確かに変額保険はややコストが高く見えるかもしれませんし、自分でできる方やわざわざ保障と資産形成をセットになった商品を選ぶ必要もないでしょう。
私のような相談型のFPに定期的な面談やサポートを依頼すれば、同様のコストは確実にかかります。そう考えると、変額保険の手数料はそれほど過剰なものではないのです。
しかし、そうした運用管理を信頼できる保険の担当者に任せたい、あるいはまとめておきたいという人にとっては、変額保険に含まれる手数料は“相談料”や“管理料”と考えても妥当と言えます。
経営者さんには法人契約で介護保障つきの変額保険を契約し、法人で保険料を払ってリタイアする際には退職金の一部として個人に名義変更する方法などを提案する場合もあります。介護保険金等の形で生前給付として受け取ると利益が出ていても非課税で受け取れますので、将来の介護資金として持っておくのも良いでしょう。
結論として「そんなに目くじら立てて否定するもんじゃないよね」ということです。
これが今回、元生命保険の募集人で相談型のFPをやってる私がデータと経験に基づいてたどり着いた率直な感想です。資産形成と保障のバランス、そして自分に合った設計のあり方を丁寧に考えれば、変額保険は「選択肢のひとつ」として十分検討に値する商品だと言えます。。
ただし、上記の通り、目的に合ってない提案をしてくる人も少なくはないので、投資のリスクや保障の機能やコストのことを話せずあまりに安易な売り方をしてくる人もいるので注意です(そもそも意向把握義務違反の可能性大)
「商品に罪は無い」
「契約の良し悪しは目的と提案する人次第」
ということになります。
私個人的には変額個人年金は優秀なアクティブファンドを割安で買えて、更に私が愛用する3%ポイント還元のクレカで保険料も支払えてポイントもザクザク貯められるのでお気に入りです。
※このコラムは一般的な保険商品の考え方、資産形成の考え方について記載したコラムであり、特定の商品の勧誘、販売を目的としたものではありません。
※保険商品の詳細については生命保険会社、募集資格を持つ方からしっかり説明を受け、納得してからご判断されてください。
※保険会社によって商品の仕組や制度の取り扱いが異なる場合があります。