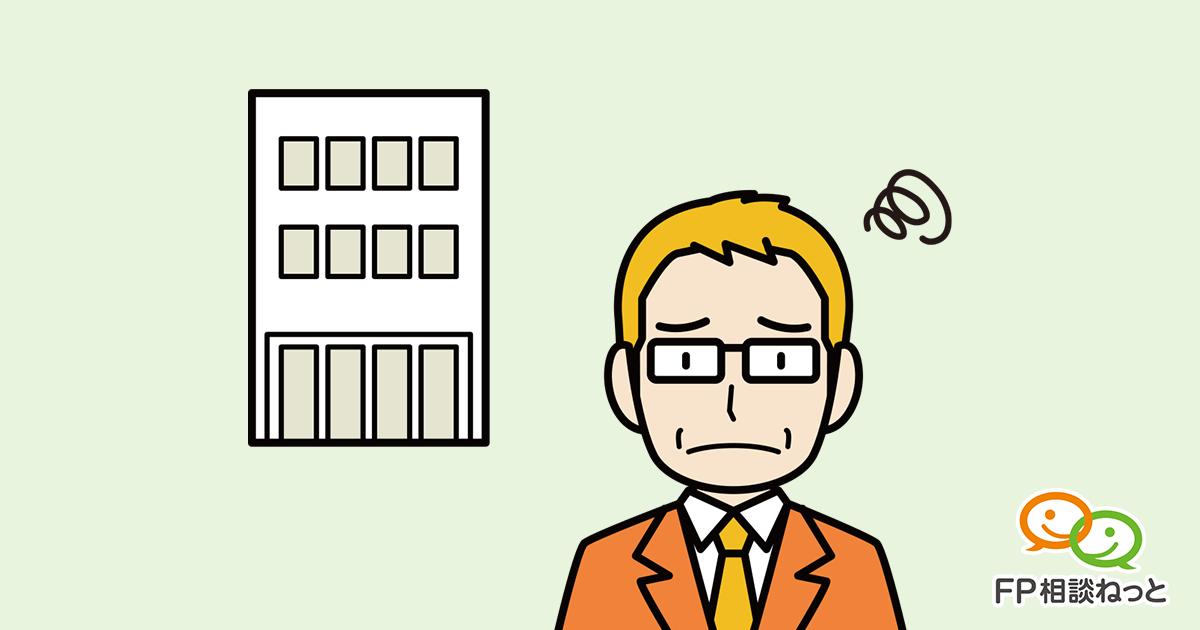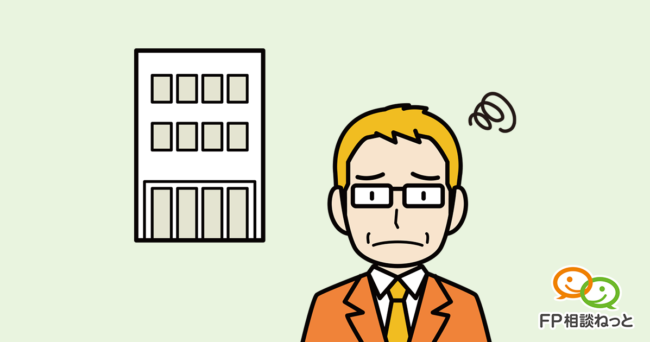相談者様DATA
【お名前】鬼塚様(仮名)
【年齢】 59歳
【職業】 自営業
【性別】 男性
【家族構成】 独身
相談しようと思ったきっかけ(アンケート抜粋)
大学院卒業後、企業で働きましたが精神的にも体力的にもキツく、早期退職制度を利用して54歳で退職しました。退職の際に「勤続27年か。65歳になれば年金を貰えるよ。」と言われたので、退職金もあるし、失業保険もあるし、退職後はふらふらと仕事をしたりしなかったり。しかし、2年前から一発奮起で起業をして、軌道に乗ってきたところです。
つい先日が誕生日だったのですが、水色の封筒に入ったねんきん定期便がきました。いつものハガキの定期便はなんとなくゴミ箱に直行でしたが、さすがに大きな封筒で届いたもので、今回、初めて中身を見てみました。
そこに、65歳から貰える予定の年金額が書いてありましたが、厚生年金分はそこそこですが、国民年金の金額が少ないのにビックリ!学生当時、国民年金には入っても入らなくてもどちらでも良かったので入りませんでしたが、それが影響したようですね。
事業も軌道に乗ったばかりですし、年金を頼りにする生活はまだまだ先のつもりでいます。しかし、60歳を目の前にして今さらですが、過去の年金未加入期間が気になっています。なんとかなりませんか?
お話した内容
年金未加入期間がある50代、今さら増やせない?
平成3年4月1日より、20歳以上の全ての国民が国民年金に強制加入するようになりましたが、それ以前の学生は任意加入でした。入りたい人だけが入れば良かったのです。よって、鬼塚さんは学生時代は未加入だったのですね。(未加入時に障害を追ったりすると、障害年金が受け取れないなどありますが、その間幸いにも何も無くて、良かったですね。)
しかし、その為に、これから60歳になるまで保険料を納めても過去7年分(学部生の2年間と大学院の5年間の合計7年間分)の年金額は受け取れません。国民年金(基礎年金)は、20歳から加入して60歳になるまでの40年掛けないと満額を受け取る事が出来ないからです。令和3年度の国民年金は満額で780,900円ですが、7年間分未納があるということは780,900×33/40≒644,242円で、月にすると約1万円足りなくなってしまいます。
厚生年金部分が有るといっても、ちょっと寂しいですね。
今さら・・ではなく、今からでも出来ることはあります。実は60歳以降も年金保険料を納めることで、65歳から受け取る公的年金を増やすことが出来るのです。
方法は二つ。国民年金の任意加入。そして、もし今後法人成りをされるということであれば、もうひとつの選択肢、厚生年金に加入することで国民年金の部分を増やすことができます。
国民年金の任意加入
まず、60歳以降も国民年金に加入する方法をご紹介します。以下の要件を満たす必要があります。
(引用元 日本年金機構HP 任意加入制度https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/20140627-03.html)
・日本国内に住所があり60歳以上65歳未満である
・老齢基礎年金の繰上げ受給をしてない
・20歳~60歳未満の保険料納付月数が480月未満である
・厚生年金・共済年金に加入していない
・日本国籍を有しない場合、在留資格が医療・観光等の「特定活動」ではない
また、日本国籍であれば外国に住所がある場合でも加入出来ます。そして、加入期間が10年に満たない場合は、70歳まで任意加入をする事が出来ます。
鬼塚さんの場合、過去の未納期間は7年ですが、すでに年金制度には厚生年金含め10年以上の加入があるため、65歳になるまでの5年間しか任意加入が出来ません。それでも、16,610円(令和3年度)を5年間納めると、780,900円×5/40≒97,612円増えます。結構大きな金額ですね。
それだけでなく、国民年金保険料は保険料全額所得控除出来ますから節税メリットもあります。
注意する事は、任意加入は申出をした月からですから、遡っては出来ないことです。
FPにお金の相談してみませんか?

老齢厚生年金の経過的加算
次に、60歳以降に厚生年金に加入する場合です。今後事業を法人化する場合は考えられる方法です。仮に法人成りすると、1人社長でも70歳までは厚生年金に加入することになります。
ここで少し60歳までの厚生年金保険料についておさらいをします。厚生年金被保険者の保険料は標準報酬月額という給与ランクによって決まります。国民年金保険料は収入に関わらず定額ですが、厚生年金保険料は収入よって違うんですね。ただし、厚生年金の保険料には、国民年金部分も含まれていて、厚生年金に加入することで、将来受け取る老齢基礎年金部分(国民年金から支払われる老齢年金)も増える仕組みになっています。
しかしながら、国民年金は60歳までが加入の義務であることから、60歳以降は仮に収入が変わらず毎月支払う厚生年金保険料が同じであっても、老齢基礎年金額を増やすことは出来なくなるのです。しかし、定額部分の被保険者期間の上限(480月)に達していなければ(国民年金部分の加入期間とお考え下さい)、60歳~64歳の厚生年金加入により経過的加算に反映されます。
令和3年度の経過的加算は、次の式で計算されます。
(引用元:日本年金機構HPhttps://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/jukyu-yoken/20200306.html)
[1,628円×生年月日に応じた率×厚生年金保険の被保険者月数]
-[780,900×20歳以上60歳未満の厚生年金保険の被保険月数)/加入可能年数×12]
つまり、60歳以降も厚生年金に加入すると、
[1,628円×生年月日に応じた率×厚生年金保険の被保険者月数]
が増加するという意味です。具体的に言えば、鬼塚さんの場合、生年月日に応じた率は令和3年度再評価表により0.936ですから、60歳以降も1年加入期間が増えるごとに、1,628円×0.936×12≒18,286円分の経過的加算が増額します。ここでも480ヶ月という上限があるため、7年分は無理ですが、5年分約9万円の年金を増やすことが出来るのです。
これ以外にも、厚生年金は報酬比例部分があります。経過的加算部分は被保険者期間の上限480月までしか加算されませんが、報酬比例部分については加入していた全期間が反映される、つまり厚生年金部分は70歳まで働くことにより金額を増やすことができるのです。
ここまでをまとめると、過去の未納によって老齢基礎年金は満額受け取れない場合、60歳以降国民年金に任意加入する、あるいは厚生年金に加入することで、老齢基礎年金を増やすことができる。任意加入の場合、増やせる金額は老齢基礎年金だけだが、厚生年金の加入を継続すれば老齢基礎年金と老齢厚生年金も増やせる、ということになります。ただしいずれも未納7年分ではなく5年分となります。
法改正で、国民年金に加入出来るのならiDeCoの加入が65歳まで可能に
2022年5月より、60歳以降の国民年金加入者はiDeCoに加入が出来るようになります。受け取り開始年齢が2022年4月より75歳まで引き上げられるため、60歳からの開始でも15年の非課税運用期間があります。
7年間の未加入期間全てを、5年間の国民年金の任意加入や厚生年金年加入によってカバーすることは出来ませんが、iDeCoを上乗せすることで少しでも多く老後資産を殖やしましょう。
掛金の限度額は、国民年金の任意加入の場合は月6.8万円、厚生年金の場合は月2.3万円(企業年金が無い場合)です。
たった5年間でも、国民年金任意加入の場合は最大408万円の掛け金を、厚生年金の場合でも最大138万円の掛金を拠出することが出来ます。掛金は全額所得控除となりますから、税負担も軽減されます。
60歳になられたときに国民年金任意加入とiDeCoの継続、法人成りされたら厚生年金に加入と掛け金の変更をして行けば良いのです。
もし、どんどん事業が拡大し業績が良好であれば、iDeCo+や、企業型確定拠出年金の導入もありでしょう。iDeCo+は上限が23,000円ですが、22,000円まで事業主負担(会社の経費として拠出が可能)にする事が出来ます。企業型の場合は、掛金最大5.5万円70歳まで加入が可能です。ただし、企業型の導入時や月々の手数料の会社負担分が大きいので、その点を注意する必要があります。
法人成りをするかどうかは、事業の現状を踏まえての計画によります。しかし、老後のお金を少しでも多く準備したいということであれば、老齢基礎年金を増やすことと、その年金加入期間を利用して、iDeCoにも上乗せ加入されてはいかがでしょうか。
~相談を終えて~
「働き続けること」だけで実は老後の年金を増やせることができるということを知り、鬼塚さんは安心されていました。
今までの老後のイメージは、60歳定年退職後、作った老後資金を取り崩す生活が始まるというものでしたが、定年年齢近くから事業を始める人もいます。現役でバリバリ働き続けて、70歳過ぎても年金を受け取ってない人もいます。人間、没頭して何かをやっていると、何時までも頭と身体の健康は保たれるものです。
事業が好調な鬼塚さん、次回は法人成をすると実際どのようなメリットがあるのか、考えるべき注意点があるのかなどを教えて欲しいとのことで、アポイントをとっていかれました。
【参考】
FPにお金の相談してみませんか?