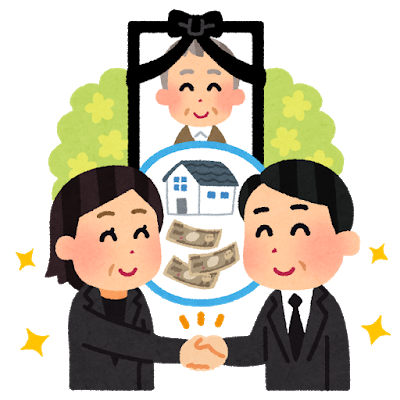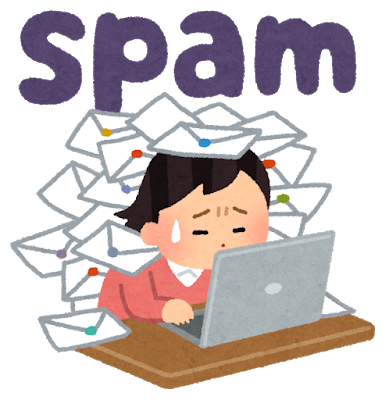『仕組みや制度を知ることで暮らしにゆとりを』
確定拠出年金相談ねっと認定FP林です。
約40年ぶりに相続法が改正されました。
原則、2019年7月1日、施行されます。
いろいろな相続にまつわる「困った」を軽減するものです。
高齢の配偶者が追い出されないために
配偶者の居住権を保護するため、分割協議が終了するまで配偶者は無償で住み続けることができたり、配偶者居住権が新設されるなど、残された配偶者が済むところが無くなってしまわないよう改正されました。
同居を条件に、どうせゆくゆくは長男のものになるのだからと土地建物を長男に名義変更をした結果、家を出なければならなくなる話はなくなるでしょう。
配偶者の居住権を保護する改正は2020年4月1日に施行されます。
自筆証書遺言、労力が少なくなり安全に
自筆証書遺言の財産目録を自筆以外でも可能となる改正は、2019年1月13日から始まっています。
財産目録をパソコンで作ったり、誰かに作成して貰ったりできるので、労力が少なくて済むようになります。
また、自筆証書遺言書が法務局で保管される制度の創設は2020年7月10日に施行となります。
こっそり、うっかりがなくなります。
ファイナンシャルフィールド『遺産相続を巡る争いが2020年7月10日以降なくなるかもしれないワケ』
都合の悪い遺言書をこっそりと破り捨てられる・・ことがなくなるでしょう。
最も、遺言書が自分に都合が悪い内容だからと破って捨てると、民法195条5号により相続欠格となります。(その前に、検認前に開けてはならないのです。)
ただ、安全に保管はされますが、有効な遺言書かどうか書き方までチェックしてくれるのではありません。
口座凍結!でも、相続人単独で引き出せる
さて、親がご臨終となったとき、誰からともなく「銀行口座の凍結前に預金を引き出さないと!」と言う声を良く聞きました。
故人名義の銀行口座は相続財産になるため、一旦凍結されたら、戸籍等相続人である事を証明できる資料と相続人全員の同意の判子を集めない引き出せないからです。
口座振替も出来なくなるので、故人の扶養家族は困ってしまいます。
それが、そこの預金口座の金額のうち、自分の相続分の1/3かつ最高150万円まで、相続人単独で引き出せるのです。
『名義人が亡くなった!口座凍結前に急いでお金を引き出す必要がなくなる?法改正のポイントとは』
お嫁さんの貢献にも
他に、
・相続人以外の人が被相続人への貢献を、相続人に請求することが出来る方策
・遺言で承継された財産は、登記など対抗要件を揃えなければ第3者に対抗できない
・婚姻期間20年以上の配偶者への居住用不動産贈与の持ち戻し免除
など、実情に合わせられた改正となっています。