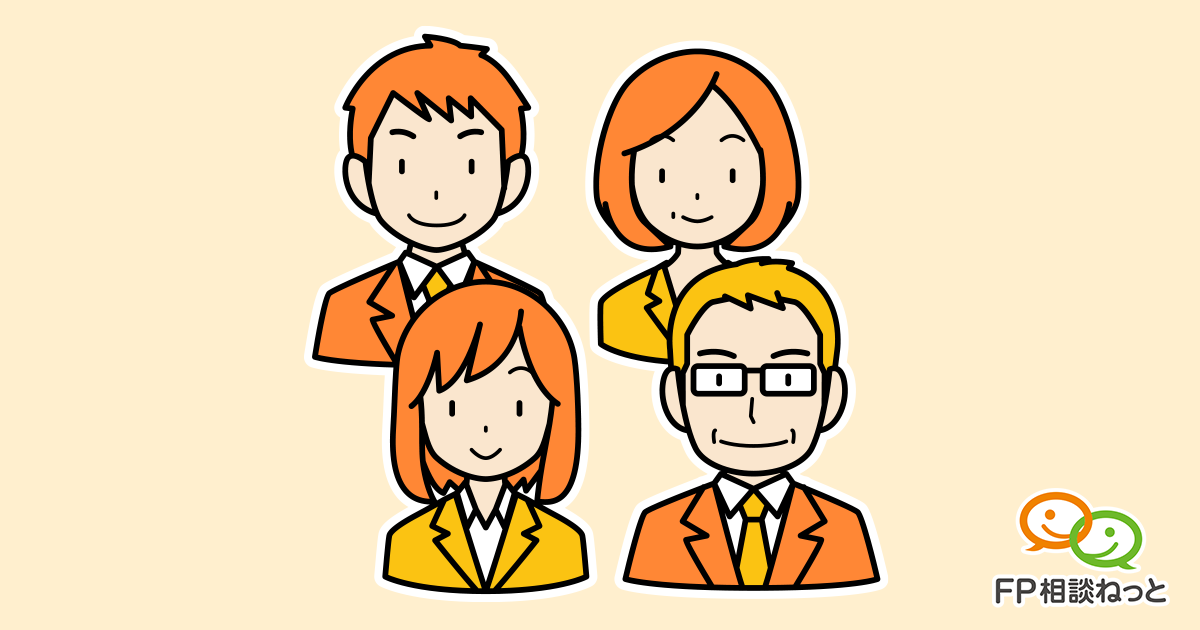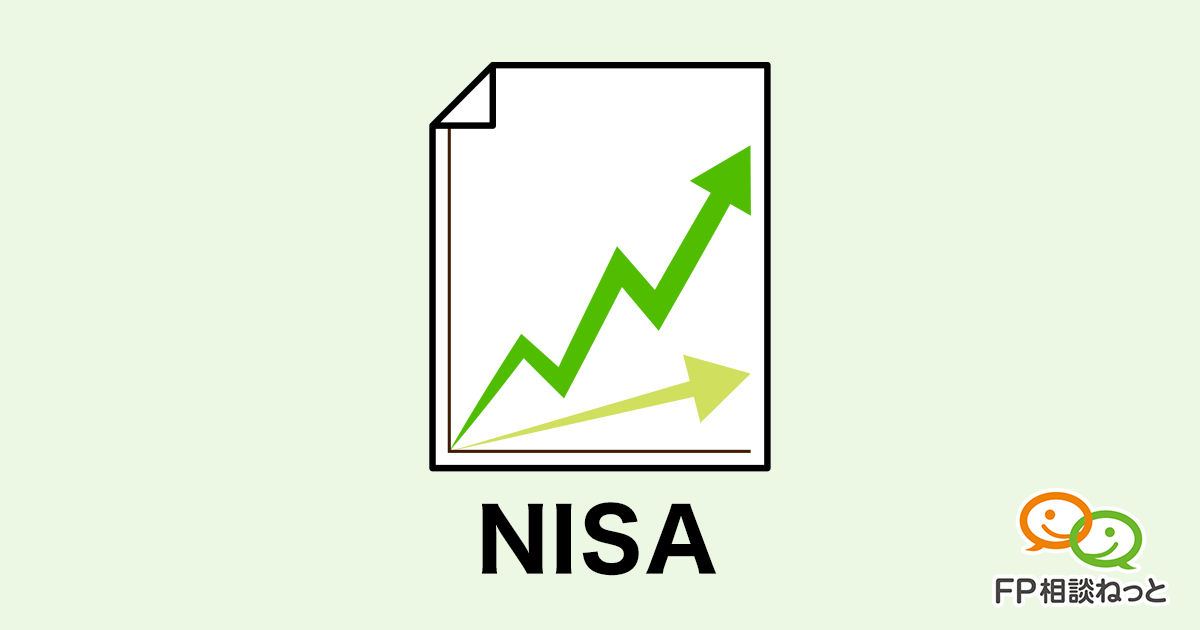2020/1/18 更新
ご相談者様DATA
【年齢】35歳
【職業】会社員
【性別】男性
【家族構成】配偶者
相談しようと思ったきっかけ(アンケート抜粋)
勤務先で選択制の確定拠出年金を導入するという話を聞いたが、よくわからずどうしたらよいか迷い、ネットで検索して近くのFPに聞いてみたいと思った。
ご相談内容
会社で確定拠出年金の制度を始めると聞きました。加入するかどうかは本人の希望しだいです。加入する場合、給料として受取る代わりに積み立て、金額は3,000円~55,000円の範囲で自分で決められるそうです。投資経験がないので運用がどんなものかもわからずどうしたらよいか迷っています。ネットで検索していたら、住まいの近くでFP相談を行っていると知り、相談に来ました。
ご相談でお話した内容
選択制の企業型確定拠出年金とは
ご相談者の会社のように、本人の希望性で加入が決められる確定拠出年金の制度を「選択制」と呼んでいます。選択制の確定拠出年金は、企業が確定拠出年金制度の導入に合わせ、給料の一部を生活設計手当てなどの名称で、退職金の前払い扱いの区分に改め、その範囲で従業員の選択により今までどおり給料として受け取るか、確定拠出年金に積み立てるかを決められ、従業員の自助努力により老後に向けた資産形成をはかることができる制度として導入するケースが増え、最近注目されています。
今回のご相談者様は、会社でこの制度を導入することを知りましたが、まわりの同僚は良くわからないからやめておくという方が多い中、最近マスコミで確定拠出年金は有利な制度として取り上げられていることが気になり、本当に有利なのか知りたいと訪ねていただきました。
iDeCo(個人型確定拠出年金)と違い運営管理機関への手数料負担はすべて会社がするので、選択制の企業型確定拠出年金加入者は運営管理機関への加入者手数料分得することになります。また、iDeCoにおいては月額23,000円(年間276,000円)が掛金の限度ですが、企業型確定拠出年金においては会社の制度設計によっては月額55,000円(年間660,000円)まで積み立て可能となります。
確定拠出年金を利用することは基本的に税制面において優遇されていますが、選択制の確定拠出年金には特有のデメリットもあり、よく理解した上で加入するか否か決める必要があります。
具体的には、確定拠出年金に積み立てる分だけ給与水準を引き下げることになりますので社会保険料等の決定要因となる「標準報酬月額」が下がるケースが多く、厚生年金保険料等の支出が減る反面、将来の厚生年金の受給額が減る要因になります。他にも傷病手当金、出産手当金、といった健康保険制度からの給付や雇用保険の基本手当て、育児、介護休業給付金を受ける場合の金額も減る要因となりますので、ご相談者様の状況を伺いメリットデメリットなど試算しながらご相談させていただきました。
家計の状況
まず、家計の状況をお聞きし将来の家計収支の状況を伺いました。奥様も会社員で、将来お子様が生まれても働き続けるお考えです。お子様は1人だけ欲しいというご希望です。結婚して3年目になりますが、1年あたり200万円ほど貯蓄できている状況です。両親も都内在住で戸建ての持ち家があり将来はご相談者様が引き継ぐことになるのですが、10年後位には建て替えが必要になりそうなので一緒に資金を出し2世帯住宅を建てたいので自分もローンを含め2,000万円くらいは負担して欲しいと親に期待されています。お子さんは中学までは公立、高校、大学は私立にいけるようなゆとりは持っておきたい意向です。
予想キャッシュフローを確認した結果、45歳ごろの住宅資金の出費とお子様が高校、大学と進まれるであろう50代半ばから60歳くらいまでの年間収支は悪化しますが高校大学で1,000万円の教育費の支出を見込んでも60歳の頃4,000万円くらいの貯蓄が出来る想定が出来ました。将来のインフレ率等読めない数字も勿論ありますが、毎月2万円位を60歳まで使えないお金にすることは問題がなさそうです。
FPにお金の相談してみませんか?

メリットデメリット
現状での報酬月額が35万円なので、年間の社会保険料は624,672円と想定できます。仮に2万円を毎月選択制の企業型確定拠出年金に積立てると報酬月額は33万円となり、社会保険料負担は589,932円と34,740円負担が軽くなります。仮にこのままの給料が続くと仮定すると60歳までの25年間で868,500円社会保険料負担が軽くなります。一方、65歳から受取れる老齢厚生年金は1年あたり32,886円減ってしまいます。65歳から90歳までの25年間厚生年金を受取ると仮定すると822,150円の減額となりこれ以上長生きをすると社会保険料の軽減分は吹き飛びます。
選択制加入2万円
年間 | 25年間 | |
社会保険料減額効果 | 34,740円 | 868,500円 |
老齢厚生年金額の減額 | 32,886円 | 822,150円 |
もちろん、月2万円を拠出することで60歳から自由に使える「自分年金」600万円を準備できることは大きなメリットです。更に運用益が非課税となりますから、上記社会保険料の損得比較だけが重要ではありませんが、間違いなく考慮すべき点でしょう。
影響はこれだけではなく、健康保険から出る出産手当金98日間で43,806円の減額(ご相談者様は男性ですので実際には影響しません)、傷病手当金では最大一年半で241,380円の減額、この他育児休業給付金や、介護休業給付金などにも影響がどの程度出るのかを確認しました。
選択制加入2万円にデメリット
・出産手当金98日間で43,806円の減額
・傷病手当金では最大一年半で241,380円の減額
・その他育児休業給付金や、介護休業給付金などにも影響
次に所得税、住民税について確認し年収420万円から年収396万円に下がる場合の所得税、住民税のモデルケースでは年間23,800円ほどの節税になり、年収、税制ともに変わらないと仮定して25年間では595,000円の効果が望める試算結果を提示しました。
そして受け取り時ですが一括受取を60歳で出来る制度なので総投資金額600万円そのままと仮定すると退職所得控除が1,150万円あるので、退職金の見込み額500万円と合わせても全く課税されないか、投資成果が出て増えたとしてもかなり軽減された税額となります。
iDeCo(個人型確定拠出年金)であれば自分で管理手数料等負担する必要があり、最低でも年間2,004円、25年間で5万円は負担する必要(選択する運営管理期間によりその3倍以上コストが必要な場合もある)があるのですが、企業型の場合そういったコスト負担は会社がしてくれて、個人は信託報酬等の負担のみとなります。一方選択制の企業型確定拠出年金には加入せず、iDeCoを選び23,000円の範囲内で積み立てる場合は一旦給料として35万円を受け取ることになるので社会保険料は下がらず将来の厚生年金等の給付金額に影響はなくなります。そしてiDeCoに積み立てた分だけ所得控除(小規模共済等掛金控除)として所得税、住民税の軽減メリットを受けることが出来ます。
選択制を選ばずiDeCoを選ぶ場合
・コストが年間最低2,004円、運営管理機関によってはその3倍以上
・所得控除については年末調整もしくは確定申告することにより、選択制と同様の効果
・社会保険料減額されず、したがって給付の減額もなし
確定拠出年金は運用成果の不確実性があり、運用経験のない相談者様には取り組みにくい面も感じられました。まず、定期預金など元本確保できる商品も確定拠出年金の中には品揃えとして準備されていることを確認しました。長期で見た場合の株式の成長性や気軽に分散投資が出来る仕組み、機動的な運用は出来なくてもある程度は市場の動きをみて、例えば債券について今は投資しなくても将来金利水準が上がったらある程度シフトするといった、ご相談者様がインターネットを通じて自分の将来の年金を管理できることに興味をお持ちいただきました。
自己責任による判断
国が用意してくれた確定拠出年金という非常に優遇している制度ですが、使い方や、企業の制度設計によっては不利に働く場合もあります。厚生年金保険料の等級を下げる形で軽減した場合、例えば若くして障害厚生年金を受給するような場合、長期にわたり障害厚生年金を受給することになり、大きく影響を受けてしまいます。厚生年金制度は社会的に維持していけるのかという不安がある一方、受給し始めてから亡くなるまで生涯にわたって受けられる制度ですので出来るだけ減額されないようにしておきたいと考えています。
ご相談者様は、厚生年金への不安が強く自分の責任で将来受け取れる一定額を確保していくために確定拠出年金の制度を使うことを決められました。その上で会社での選択制の企業型確定拠出年金加入以外にiDeCoの選択肢があることがわかったので迷われました。2017年1月から、選択制の確定拠出年金を企業が導入していて月額55,000円の枠が設定されていても、本人がそれに加入を希望しない場合、個人でiDeCo加入が可能になり、選択肢が増えました。
奥様もしっかり働いていかれることもあり、国の社会保険の制度に頼らずに自分の手で資産形成をより有利な仕組みを使って準備したいと考えられました。確定拠出年金だけでなくNISAなども活用して年金資産以外の貯えも早めに準備していくこと、仕事のスキルをさらにアップさせ、給料水準が上がったら確定拠出年金への積立額は23,000円を超えて利用することも視野に入れて、選択制の企業型確定拠出年金に加入される意向を決められました。
今回の決断は会社で導入する確定拠出年金で運用できる投資信託の品揃えが、iDeCoで利用できる運営管理機関と比べて遜色ないこと、途中で厳しくなっても少なくとも3,000円は積み立てる自信があること、住宅ローン控除を受け税額控除を受けても尚節税効果が見込めることなども判断材料になったようです。近日中にNISAもあわせ、具体的な運用ポートフォリオを相談する予定です。
※会社の確定拠出年金に加入をすると、転職時にすべての運用商品を現金化して次の制度に資金を移す「移換」という手続きが発生します。一方iDeCoであれば、転職をしても運用商品を現金化する必要がありません。(転職先が企業型確定拠出年金を導入していても、運用指図者として運用商品を売却せず運用を継続できる)。例えば転職を予定している方の場合、会社の選択制を選ばずiDeCoにしておく方が良い場合もあります。あくまでもお客様のお考えにもよりますので、ご不明な方はご相談下さい。
FPにお金の相談してみませんか?