家計の見直しは固定費からというし、保険を見直そう!
でも、そもそもいま入ってる保険の何を見直せば?
保険って何のために必要だっけ?
成人の8割が加入している生命保険ですが、その一方で加入している保障内容については半数以上の方がよく理解していないという調査結果があるようです。
実際に私が相談を受ける内容のTOP3にはいつも「保険について」が入っています。
今回そんな保険に関する疑問を解決するために、
大人たちがずっと学び続けるコミュニティSchoo(スクー)で生放送授業を行いました。
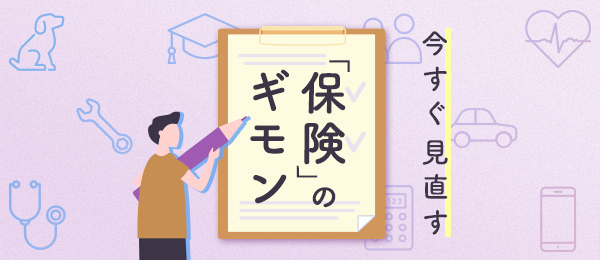
* 保険が必要な人はこんな人
* 保険に入っているひと
/入る前のひとのためのチェックリスト
* 保険を見直すタイミングについて
* ななこママの相談コーナー
(※ななこママは私が運営するYoutubeチャンネルのキャラクターです)
やはり保険のことに関しては大変関心が高く、当日は男性・女性が半々ぐらい。
10代~70代(!?)と幅広い年代から、371名の方が受講してくださいました。
なるほど!が飛び交う授業
授業は生放送で、感想や質問を入れながら参加していただくことができるため、たくさんのコメントをいただきました。
特になるほど!が飛び交ったのは、
「貯金は三角・保険は四角」
「保険に入っても、何かが「起こる可能性」は1%も下がらない!」
「こんなセリフに気を付けろ!」
「遺族年金もらえる人、もらえない人」
「あなたに合ってない保険はズバリこれ!」
「意外と知らない見直しのタイミング」
などですね。
さらに、ナナコママが登場すると教室がガヤガヤ!?笑
「ママ!」「ナナコママ!」「スナックナナコで保険相談開いて~」などヒートアップ!
キレッキレの回答でバシバシ質問にお答えしました。
何とな~く聞きにくい質問も、ナナコママになら聞きやすかったかもしれません(笑)

他にも
- この授業面白い
- 先生の愛を感じる
- とても為になり面白かったです。
- お金の問題ってとっつきにくい印象でしたが、すごくわかりやすかったです。
- 先生のコメントの切れ味が素晴らしい。
- 先生の引き出しが多い!
など、嬉しいコメントをたくさんいただきました。
1時間という限られた時間での授業だったので、いただいた質問にお答えする時間が圧倒的に足りず、なんとか拾えたいくつかにだけお答えするにとどまりました。全部にお答えできずにごめんなさい。
いただいた質問やコメントは全て拝見し、今後も動画やブログでご回答していきたいと思っています。
アーカイブ視聴も可能です
生放送を見逃した!
今ごろ気になってきちゃった・・・
そんな時は、授業を今からアーカイブ受講することも可能です▼
schoo.jp/class/8591?ref=tchr
自分に合った保険に加入するためには「知識+自分の場合で計算」の両輪が必要。
相談『前』に確認しておくことで、よりスムーズに保険の加入や見直しができるようになりますよ!
ぜひ今からでも学んでみてくださいね。