こんにちわ、ー家計円満は夫婦円満!ー プレ定年夫婦専門FPの三原由紀です。
お子さんが20歳になると「国民年金の加入と保険料のご案内」が送られてきます。
20歳で学生の場合、親に扶養されている人が多いかと思います。
ですから、子供自身で納付を考えるというよりは、各ご家庭で考えられるのではないでしょうか?
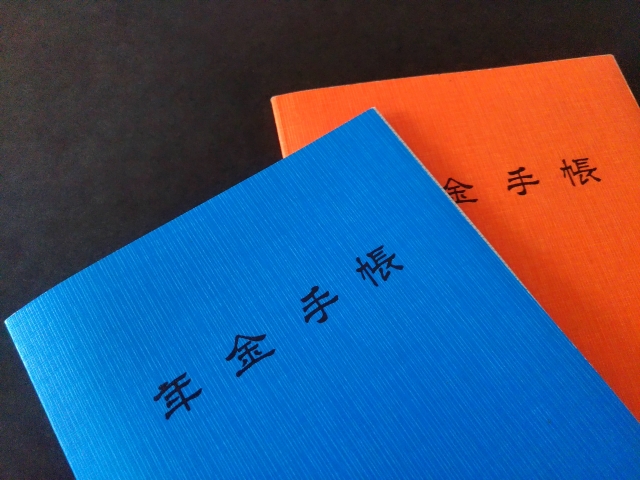 こ
こ
学生でも20歳になったら国民年金は強制加入です
国民年金は、基本的に日本国内に住む20歳以上から60歳未満のすべての人に加入義務があります。
ただし、厚生年金に加入している場合には第2号被保険者となるので、自動的に国民年金加入することになります。
20歳で大学生や専門学校生であっても例外ではありません。
ただし、学生の場合、国民年金保険料を納めるのが難しい人も多いでしょう。そのような時には「学生納付特例制度」を利用することで在学中の保険料の納付を猶予することができます。その際には、以下の要件を満たす必要があります。
本人の所得:118万円+扶養親族等の数×38万円
上記要件は本人に限りますので、両親など家族の所得は問われません。
注意したいのは、アルバイトをして上記所得を超えた場合です。今は、時給仕事ではなく、インターネットを利用して収入を得られますので気をつけたいところです。
また、対象となる学校については、大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、特別支援学校、専修学校及び各種学校 、一部の海外大学の日本分校に在学する方、 夜間・定時制課程や通信課程の方も含まれますので、ほとんどの学生の方が対象となります。対象か不安な場合は、学生納付特例対象校一覧を確認しておきましょう。
学生納付特例制度の手続きどうするの?
手続きについてはとてもシンプルです。
次の順序で進めていきます。
- 国民年金加入案内を受け取る
20歳の誕生日から2週間程度で「国民年金の加入と保険料のご案内」が管轄の年金事務所から届きます。学生納付特例制度の申請書も同封されています。万が一届かない場合には、行政の国民年金課か管轄の年金事務所に問い合わせをしましょう。
- 国民年金保険料学生納付特例申請書を提出
学生証のコピーを貼付して行政の国民年金課か管轄の年金事務所に提出します。
学生納付特例の申請年度は4月から翌年3月までですので、次年度以降は「新年度の手続き案内」が送られくるので返送することで手続きを行うことができます。
猶予した保険料はどうすればいいの?
猶予した保険料をそのまま放置すると、65歳以降受給する老齢基礎年金を満額受給することができず減額となってしまいます。
保険料の後払い(後納)をすることで、老齢基礎年金の年金額を増やすことができます。
なお、追納ができるのは追納が承認された月の前10年以内の免除等期間に限られています。(例えば、平成31年4月分は令和11年4月末までです)
保険料の猶予を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降に保険料を追納する場合には承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます(例えば、令和元年度に猶予した場合、令和4年度以降は加算保険料を支払うことになります)
親が代わりに納めて出世払いの方法も
最後になりますが、我が家が行なった方法についてシェアさせていただきます。


子供の国民年金保険料を親が納めることで、親の納税額を減らすことができます。というのも国民年金保険料は社会保険料控除に該当するので、所得税・住民税が軽減されるのです。我が家の場合、子供の国民年金保険料を2年前納したことで、その年の所得税と住民税を軽減することができました。一般的に親の所得は20代の子供より高くなりますので、親が社会保険料控除をした方が還付する税金は多くなります。
例えば、2年前納の保険料379,640円(令和元年度保険料総額+令和2年度保険料総額−15,760円割引額)で計算してみましょう。親の所得税率20%と子供の所得税率10%で計算すると37,964円の税額が減ることになります。
親が代わりに子供の国民年金保険料を納めて、子供が収入を得てから分割払いをすることで両者にとってメリットがあると言えるでしょう。その時の保険料については親子で話しあって決めると良いかと思います。
国民年金の保険料を納めることは義務です。
どうせ学生時代の保険料を納めなくていいからと放置していると、万が一ケガや病気などで障害状態になった時に障害年金を受け取ることができません。納めない、納められない場合には必ず行政の担当窓口で相談をしましょう。

