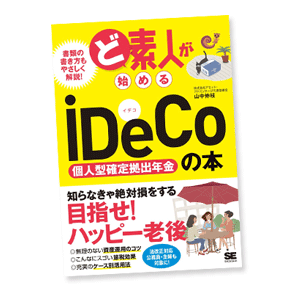除外は企業型DCで珍しいことではない
楽天証券のiDeCoのラインナップから9商品が除外されるお話ばかりをしてきましたが、実際運用商品の除外は珍しいことではありません。むしろ企業型確定拠出年金(企業型DC)においては、事業主が商品提供を行う運営管理機関を適切に評価し、加入者利益のために運用商品の選定はじめ運営業務に至るまでモニタリングを強化するによう、国が支援を行っています。
これはひとえに確定拠出年金が国民の老後の資産形成に重要な役割を担っているということと、その制度(運用商品も)の提供を行う側には、加入者の利益を最優先する責任が課せられているからです。

企業の商品見直しとiDeCoの登場
企業型DCにおける具体例で言うと、多くの企業において企業型DCの導入は2000年代前半で、導入から20年も経過しているのに運用商品の入れ替え(除外)をしていない企業が多いという点について、厚生労働省は「それって本当に加入者利益を守っているんですか?商品見直しをしないのって、会社の怠慢では?」と言っている訳です。
この20年で、投資信託における信託報酬はずいぶん引き下げられました。デジタル化であったり、グローバル化であったり要因は様々あるかと思いますが、一番の要因は2017年のiDeCoの登場ではないかと筆者は考えます。それまで企業型DCは、その会社独自の制度であるが故にクローズドでありどのような投資信託が採用されそのコストはいくらなのかなど、比較検討することができなかったからです。
しかしiDeCoの普及が始まると、多くの金融機関がこぞってプランを発表し、コスト競争が始まりました。どこの金融機関のプランがどの投資信託を採用しているのか、その信託報酬はいくらなのか一目瞭然、比較サイトでだれでも確認できるようになりました。
情報がオープンになると、当然ながらそれらの情報の比較検討が容易になり、コストの引き下げのみならずサービスの向上を求める声がiDeCoをきっかけに企業型DCにも広がったのではないかと考えます。
商品除外の意義と課題
信託報酬などのコストは投資家利益から差し引かれるものですから、状況をみながら適時運用商品を見直し、加入者のためにより良い運用商品をそろえる、そのための「除外」は本来とても重要なものなのです。
ただし、除外の過程においては、少なからず加入者は新規での積立投資ができなくなりますし、それに伴いいくつかの手続きも必要となるので、充分な理解を促す努力が運営管理機関側に求められています。
SBI証券と楽天証券の除外事例
SBI証券の除外事例と制度改正の背景
少し個人型確定拠出年金(iDeCo)における話を補足すると、過去除外を大々的に行ったのはSBI証券です。この時は、加入者利益というよりも法律が変ったことで除外せざるを得ない状況に陥ってしまったというのが実態でしょう。なぜかというと、2018年5月に確定拠出年金法の一部が改正され、iDeCoの商品数は35本以内にするように決め、結果的にSBI証券は新しいプラン「セレクトプラン」を出すきっかけになりました。
iDeCo制度の拡大とSBI証券の対応
2017年に法律が変りiDeCoに加入できる資格者の拡大があるまで、個人型確定拠出年金は非常に限られた方だけが活用している、そんな制度でした。また個人型を扱う金融機関はとてもすくなくその中でほぼ独占的に行っていたのがSBI証券でした。
そのSBI証券の個人型確定拠出年金の商品ラインナップは実に67本。それも個性の強いアクティブファンドが多数組み込まれ、投資経験が豊富な方も満足できるとその選択肢の多さは評価を得ていたとも記憶しています。
しかし確定拠出年金制度を広く国民に普及させることになり、「あまりにも商品数が多いと、結果的に商品選択ができない方も多いのではないか」との配慮から運用商品数は35本と決められました。SBI証券もこの法律改正を受け、商品数の「除外」に乗り出さざるを得なくなったのですが、最終的にはこのプランを「オリジナルプラン」と名付け2021年以降新規加入の受付を終了、それに代わって時流にもあった「セレクトプラン」を発表し現在に至っています。
楽天証券の除外とその影響
35本の制約が出てから運営管理機関に参入した金融機関はそもそも35本を目処に商品選択をしていたので、しばらく除外はないのではないかと想像していましたが、想定よりも早い段階で楽天証券が9本もの除外を発表したのはある意味衝撃でした。
6月30日までとした回答期限が果たして、加入者周知に充分な期間なのかというところ、企業型DCと異なり広く一般の方が加入するiDeCoの除外のプロセスとして楽天証券は充分なコミュニケーションをとっているのだろうかという点が非常に気になっています。
楽天証券のiDeCoは加入者も多いです。またその加入者の多くは投資経験が浅い方や若年の方が多いのではないかと考えます。突然の除外発表に不安を抱えている方はぜひFP相談ねっとのファイナンシャルプランナーなどにご相談されることをお勧めします。
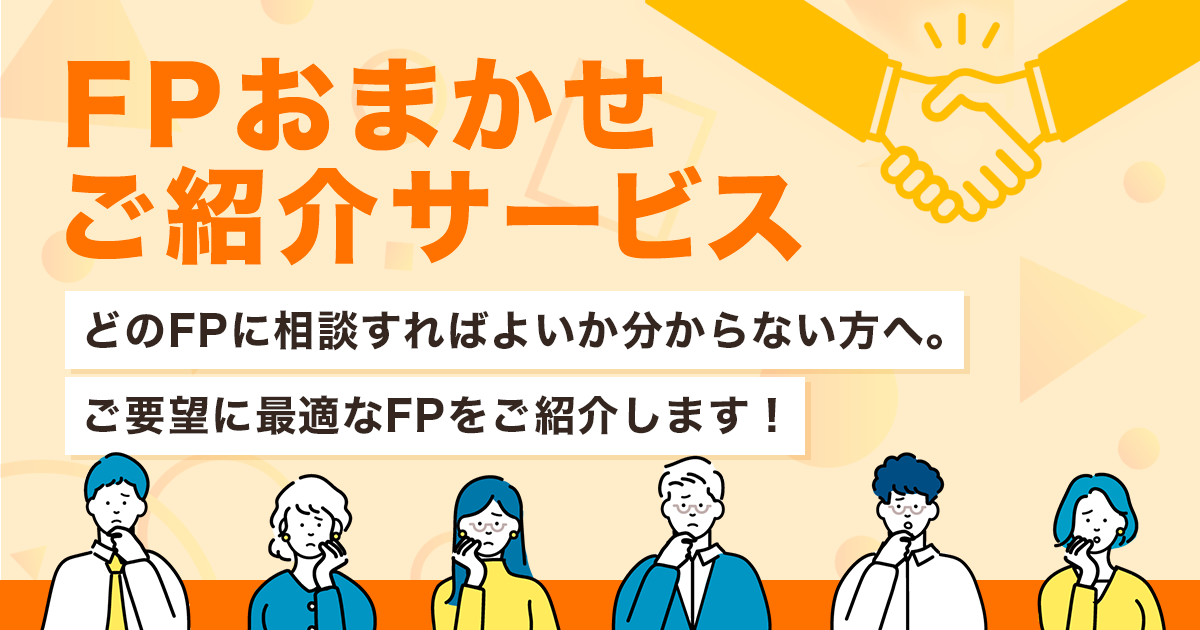
FP相談ねっと代表 山中伸枝