こんにちは。
子育て世代の家計のパートナー、FP相談ねっと認定FPの前田です。
お正月と言ったら、子どもはお年玉ですね。

そして、保育園児がお年玉をもらったら?
まずは親が管理するのではないでしょうか。
でも、そのお年玉、もし銀行に預けるなら、子どもと一緒に銀行に行きましょうね。
お年玉の使い道の考え方は、子どもの年齢によって違う
お年玉は、貯金する?それとも、使う?、ネットでは、お年玉は使わせるべきといった、お金のコラムが多いように思います。
貯金しても、使っても、どちらでも良いと思いますが、ようは、子どもに考えさせることが大切ということ。
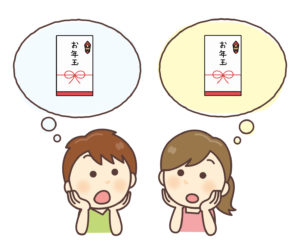
子ども自身が、買いたいモノがあり、お年玉で買おうと思っていたなら、買うのが良いでしょう。
買いたいモノがないなら、買いたいモノが出てきたときのために、貯金をするのも良いですね。
こどものお小遣いはいつから?オススメは、小学1年生
ただ、いくらあれば何が買えるか、まだ、分からない保育園児の場合は、お年玉で買いたいものってなかなか思いつかないのではないでしょうか。
(せいぜいお菓子ぐらい?)
うちの年少の娘は、お年玉をもらって、「お金とこんなの入ってた〜!」と言っていたくらいでしたから。

小銭=お金
お札=お金ではない「こんなの」
なので、結局、親が管理することになります。
そして、もし、そのお年玉を子どものお金として貯金をするなら、銀行に行くときは、ぜひ子どもと一緒に行ってください。
銀行に一緒に預けに行く体験をさせる
小学校低学年くらいになると、「銀行に行けば、いくらでもお金が出てくる」と思うようになる子どもがいます。そして、それがお母さん達の困りごとだったりします。

なぜ、子どもは”いくらでもお金が出てくる”と思うのでしょうか?
それは、銀行でお金を預ける姿を見せていないからではないでしょうか。
なので、まだ「銀行」の存在や役割を知る保育園児の時に、一緒に銀行に行くのです。
一緒に銀行に行くことで、社会には、「銀行」というところがあって、お金を預けたり、引き出したりする場所ということを覚えることができます。
我が家の場合は、近所の小さな郵便局に行きます。
なぜなら、その郵便局は、「あら、お年玉もらったの?預けるのね〜」なんて、局員さんとのやり取りがあり、最後に飴をもらえるからです。
このたった1個の飴が子どものテンションをアップさせ、銀行の記憶を定着させます。
ただ、残念ながら、銀行は平日しか営業していないんですよね。
保育園ママは、平日仕事なので、一緒に銀行に行くって、結構ハードル高いかもしれません。
その場合は、ATMでもいいと思います。
最近は、小銭対応のATMもありますし。
ATMという小さな銀行にお金を預かってもらうのです。
子どもにとって、ATMもふだんの生活では、全く利用しないものなので、ATMで入金することも銀行の記憶を定着させるでしょう。
そして、お金を預けたら、預ける意味を伝えましょう。
あるいは、子どもに質問してみましょう。

うちの子に、なぜ銀行にお金を預けたのか聞いたところ、
「えっ〜と、お金を使わないから〜」と、言っていました。
間違いではないので、良しとします。
一緒に銀行に行く子どもの年齢は?
「保育園児」とお伝えしてきましたが、保育園児も0歳〜5歳と、赤ちゃんから幼児までです。理解度はまったく違います。
なので、お金の存在を知った頃3歳、4歳くらいでしょうか。
その年齢から、一緒に銀行に行くのが良いでしょう。
また、保育園児でなくても、お年玉を貯金したいと思ったのなら、小学生でも自分で貯金をするのが良いですね。
自分でATMを操作する、自分で入金伝票を書く・・・

まだ早いかも、と思う頃から、一緒にお金の話をすることで、成長した時に、しっかりとお金を理解できるようになります。
年長や小学生になると、お母さんたちは子どもに「お金は使ったらなくなる、だから、計画的に使わないといけない」ということを理解してほしいと思うようになります。
小学校低学年でそれを理解させるなら、年少や年中から、お金の話を子供と一緒にするようにしましょう。
たった5分のお金の学校「保育園ママのための増やすお金講座」5分間動画
ところで、お年玉の由来って・・・
ところで、なんで、大人は、子どもにお年玉をあげないといけないのでしょう・・・・
お正月は、そうでなくても、出費が多いのに・・・
と、思って調べてみました。
お年玉って、昔は、お金じゃなく、お餅だったそうです。
そして、そのお餅は、ただの餅ではなく、「神様の魂」を象徴するものだったそうですよ。
そして、その魂である餅を食べることで、一年分の力がわき、元気をもらうのだそうです。
餅からお金に変わったのは、高度成長期時代だそうです。
お年玉って、風習だから、なんの疑問も持たずに、もらったりあげたりしていますが、実は深い意味があるのですね。
大人は貯金してはいけない
さて、子どもと同じように、大人も貯金・・・・
は、NGですよ。
「銀行に預けても、増えないけど、どうすれば良いか分からなくて、普通預金に入れている」なら、まずは、4日間のメール講座を受けましょう。
どうすれば良いかの方向性が見つかります。
そして、本当は、ちょっぴり興味のある資産運用、はじめましょうね。
メール講座終了後は、資産運用はじめたくなりますよ。
詳細は、こちら
「やりくりが楽になる家計のつくり方」4日間のメール講座のご案内
すぐに登録は、こちらから↓



