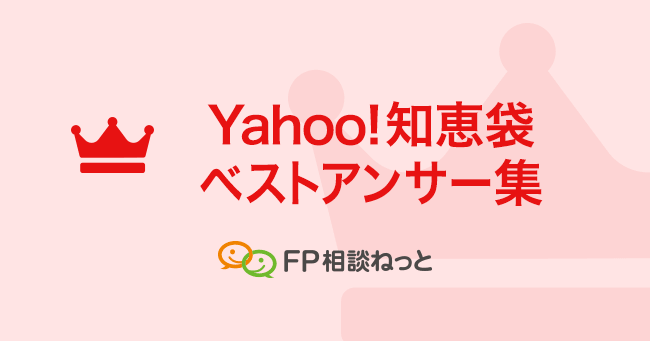確定拠出年金の専門家として、ヤフー知恵袋さんにて回答をしております
以下の記事がベストアンサーに選ばれました
chiebukuro.yahoo.co.jp/my/yc_ogweh
【質問】
個人型確定拠出年金を始めようと思っています。
向こう15年-20年ぐらいのスパンでみた場合
手数料の安いSBI証券か、スルガ銀行がいいかと考えていますが、ここからがどの材料で判断したらいいのか迷います。当初は資産50万円未満で運営管理料がかかるのでしょうが、運用商品のファンドの規模(総資産が安定しているもの)も重要と聞きました。スタンスとしては、40代で多少のリスク資産にも投資したいと考え、別個に積み立てしてる日本株ファンド、外国株債権バランスファンドとともに運用の一部と考えています。判断のヒントをお教えいただければ幸いです。
【回答】
確定拠出年金相談ねっとを主宰しておりますファイナンシャルプランナーの山中伸枝です
当初の費用でいえばスルガ銀行さんの方が安いですが、長期かつ運用商品のバリエーションでいえばSBIさんの方が良いかも知れませんね
基本的にWEBで操作をするので、機能性も確認するのもよいかもしれませんね
個人型加入マニュアルとして窓口選択の判断基準などまとめてあります
ご参考になりましたら幸いです
fpsdn.net/column/2015/03/2824.html
- ナイス! 0
質問者
2015/07/1120:55:02
ありがとうございます。モーニングスターのページは確認しそれからスルガとSBIがでてきました。
SBIにはNISA口座をつくってインデックスファンドとETFを購入しましたが、元手に限界もあり毎年100万円までは。。。という感じです。積み立て感覚で節税にもなるのは実現可能な目標とおもっていますが、銀行が増えすぎるのもいま問題なので(妻の積み立てもあわせて7行―8行ぐらい散らばっています)、ファンドの信託報酬がわずかに安めのものが多いSBIに落ち着けようかと思います。
会社員で、会社にはハンコは押しますのでご自由にといわれ、まあ毎月上限2万3千円どまりでしょうが、長期ではいくらかメリットがでてくるかとおもい当初は攻めの海外株式かREIT中心に考えてみるつもりです。やはり通常の投資とは所得控除される点が最もメリットに思えますよくお勉強されてますね
NISAと確定拠出年金は資産形成の用途別にぜひ活用したいところですね
運用商品のバランスは、ご資産全体で考えてという点では、すでに実行されているようですので、よろしいかと思いますま、ほとんどの会社さんが個人型についてはどうぞご自由にというスタンスです(笑)
口座引き落としで良いと思います