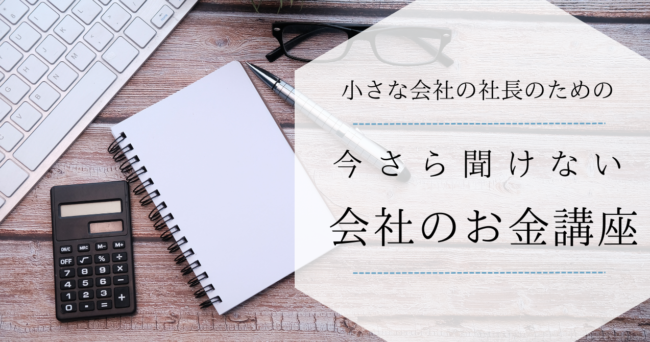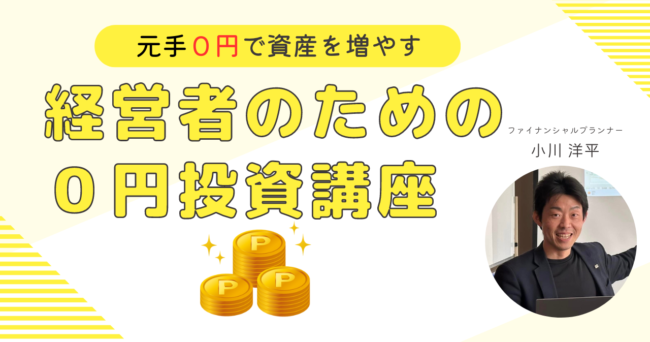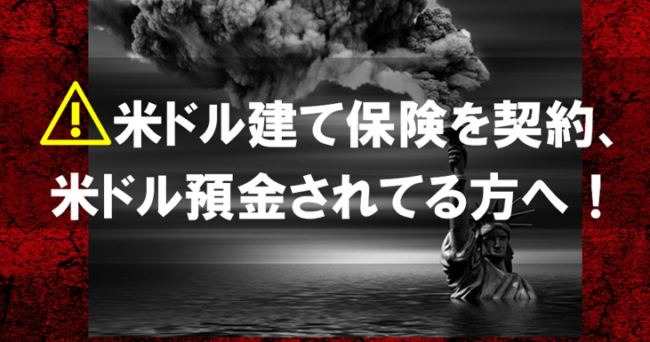こんにちは(^^)
経営者のキャッシュを増やし、資産を増やす小さな会社の社外CFO、ファイナンシャルプランナーの小川です。
先の衆院選において大躍進し、12月頃には103万円の壁の引き上げのために尽力してきた国民民主党より、金融資産の所得への課税30%に引き上げる方針という旨を発信していました。
そして、更には厚生労働省社会保障審議会年金部会においては現在の厚生年金保険料の上限の引き上げについても議論されているという発表もあり、特にX(旧Twitter)で紛糾する話題になっていました。
さて、これらの話題はまだまだ一つの案というだけで、厚生年金に関しては今年から段階的な引き上げが予定されていますが、金融所得課税に関しては実現することになってもまだまだ先のことでしょう。
負担能力に応じて税負担を増やすという考え方からすれば妥当な方向性とも受け取れますが、既に高い負担を強いられている立場では更に負担が増えるのかと思われる方も多いことでしょうし、私もそのくらいの収入の層の方が支払っておられる税金や社会保険料の金額を見ていますとその気持ちはとてもよくわかります。
ということで、そんな「大増税時代」がやってきてしまっても、資産を上手に守れる方法についてお伝えします。この方法を活用することで可処分所得を年間100万円以上増やすことも可能ですので、参考にしていただけますと幸いです。
また、当オフィスではFPが税理士、社会保険労務士と共同し、あなたに合ったキャッシュを残しつつ税負担を軽減することができる資産防衛のスキームをご提案しています。
たった一時間の初回の無料相談で行ったアドバイスだけでも年間200万円ものキャッシュを手元に残すことができたという方もいらっしゃいますのでお気軽にご相談くださいね(初回相談無料です)。
1.年収ごとの税金、社会保険料の負担は・・・?
まず、年収500万円の人と、1000万円の人、2000万円の人の税金、社会保険料の負担について、どの程度なのかを見てみましょう。

諸々の条件によっても異なりますが、家族構成や年齢などが同じ条件で、年収だけが違う場合で比較するとこのようになります。
収入が高ければ高いほど負担率は大きく、年収1,000万円から2,000万円の人を比較すると1,000万円も収入が高いのに570万円しか可処分所得が増えていないということになります。
ご自分で役員報酬を決めることができる中小企業の経営者さんは、生活に必要な分だけ役員報酬を設定することができますので、社宅を活用したりリタイア後の資金などは確定拠出年金を活用したり、退職金を活用して準備するなど、役員報酬を調整することが可能ですのでできるだけ低くしておいた方が会社にも個人にもお金を残すことができるようになります。
2.年収2,000万円の人の税金はどの程度?
次に、どの程度の税率でいくらくらい税金を払うことになるのかをみてみましょう。こちらが所得税率の一覧です。

この「課税される所得金額」とは単に年収を示すものではなく、所得から所得控除額を引いた金額になります。
例えば、給与収入が2,000万円の人の場合ですと、下記の給与所得控除を差し引いて所得が計算されます。

2,000万円ー195万円=1,805万円となります。
そして、1,805万円から、基礎控除や社会保険料控除などの「所得控除」を差し引いて課税される所得が計算されます。

こちらの確定申告書で開設すると、③に給与収入2,000万円が入り、④は給与所得控除を差し引いた後の1,805万円が入ります。
そして、⑤には基礎控除48万円(58万円に上がる方向)、支払った個人負担分の社会保険料や、iDeCoや生命保険料の掛金が入り、④で計算された所得から⑤を引いて、⑥の部分の課税される所得が計算されるのです。
仮に⑤の所得控除の金額が160万円だとした場合、
④所得1,805万円ー⑤所得控除160万円=⑥課税される所得1,645万円
となり、所得税率は33%となりますので
1,645万円×33%ー153.6万円=所得税は389.25万円を納税することになります。
加えて、住民税は基礎控除の金額や生命保険料控除の金額などが異なるため課税される所得よりも計算対象の金額は大きくなるのですが、およそ10%で計算すると164.5万円となり、所得税と合わせて550万円以上にもなります。
3.金融所得の税金はどうなる?
さて、今度は金融所得にかかる税金についてみてみましょう。
金融所得とは、株式投資によって得られた配当や売却益などを意味します。
証券口座を開設する際には「一般口座」と「特定口座」を選択することができるのですが、「特定口座」を選び、源泉徴収ありの方を選ぶと原稿制度ではその人の所得に関わらず一律20.315%の課税となります。
冒頭にお伝えした30%とは、この20.315%が30%に引き上がることを意味します。
一方、源泉徴収なしの場合や、一般口座の場合には利益を総合課税で申告し、課税されることになります。
ですので、最低税率が適用される所得層にとっては所得税、住民税合計で約15%の負担になりますので、仮に金融所得課税が30%となってもむしろ負担は少なくなります。
対して、所得が高いそうにとっては仮に総合課税なんて選んでしまえば30%じゃ済まない負担率になってしまうわけです。
NISA制度が拡充され、1,800万円の元本の利益については非課税で受け取ることができるようになりましたので、投資元本1,800万円までの部分については気にする必要はないでしょう。
しかし、それを超えて資産を保有したいという層にとっては問題ですよね。
4.中古リノベ不動産で「減価償却費」を活用する
さて、ここで搭乗するのが以前もご紹介した耐用年数を過ぎた不動産の「減価償却費」の活用です。
4年の減価償却期間を活用し、所得を圧縮することが可能です。
例えば、年間800万円の赤字(キャッシュフローはプラス)が発生している物件を買ったとしましょう。
上記で計算した給与所得1,805万円と損益通算すると、所得は1,005万円となります。
所得1,005万円ー所得控除額160万円=課税される所得845万円
Before:所得税389.25万円 住民税164.5万円 After:所得税130.75万円 住民税84.5万円
差額は338.5万円にもなります。
これが4年分ですと、税金の軽減効果は総額で1,354万円となります。
ただし、4年の減価償却期間を終えた5年後には建物部分を減価償却しきっているために減価償却を受けることができず、家賃収入の利益が積み重なることになります。
また、もしも5年経過後に売却した場合には、土地の値段が変わらなかったと仮定し、建物も購入した場合と同等の価格で売却できた場合には長期譲渡所得に該当し、減価償却費分(900万円×4年分=3600万円と仮定)で売却できた場合、20%の720万円が課税されることになります。
5年経過した後は減価償却費が減るか、売却時に課税はされますが、このように減価償却費を活用することで税金を引下げすることができ、そして売却時には長期譲渡所得の20%の分離課税を利用し課税額を抑え、そして更には家賃収入による利益も得ることができますので、節税しながらキャッシュを生むことができるのです。
もちろん、しっかり利益が出てキャッシュが残る物件でないと意味がありませんので、物件選びは信頼できる業者さんから、しっかり家賃収入と掛かる経費や返済でどの程度の利益とキャッシュフローになるのか、シミュレーションを見せてもらいながら検討していきましょう。
5.変額個人年金の活用
そして、今度は金融所得課税が強化された場合に、変額個人年金を活用したテクニックをお伝えします。
変額個人年金については以前こちらの記事でもご紹介しておりますのでご覧ください。
この変額個人年金ですが、年金で受け取る場合と、減額(一部解約)しながら取り崩していくという方法があります。
年金で受け取った場合には下記のような計算式で計算され、税金が計算されます。
①受け取る年金額のー②払い込んだ保険料÷受け取り年数=一年あたりの雑所得
仮に1000万円を払い、2000万円に増えたものを10年に分割して受け取った場合で計算すると・・・
受取額200万円ー支払った保険料相当額100万円=利益100万円
この利益100万円が雑所得となり、他の所得と合算されて税金が計算されます。
変額個人年金は通常の投資信託等と異なり、保険として保有している期間中は利益は課税されず、受け取り時に課税される特徴があります。
ですので、金融所得課税が30%になったとしても影響を受けず、年金を受け取るタイミングで所得が下がっているような場合で受け取ればもっと低い税率で受け取ることも可能です。
仮に税率15%のときに受け取ったとすると、100万円の15%ですから課税額は15万円、10年で150万円の課税で済みます。(国保は計算に入れていない)
また、減額しながら取り崩した場合にはこのように一時所得に該当し、他の所得と合算されて課税されます。
(①年金資産 ー ②支払い保険料 -50万円)×1/2=一時所得額
上記のように1,000万円の保険料を支払い、2,000万円に増え分割して取り崩した場合、まずは元本分から控除されます。
つまり、初年度で1,000万円を取り崩した場合には、保険料を1,000万円を払ってますので受け取った金額に対し利益は出ていないと見なされ、非課税で引き出すことができます。
また、50万円の控除もありますので、1,050万円まで非課税で引き出すことができるということになります。
そして、残りの950万円も、1年あたり50万円の控除を活用することができ、更に50万円を超えても1/2が所得にカウントされることになりますので、仮に60万円ずつ約16年に渡り取り崩した場合には課税される金額は年間5万円分のみです。
NISAを使わずに投資信託を保有していると、20%が課税されますので今回の場合には200万円が税金で引かれることになりますが、この一時所得の税制を活用することで数万円程度に税負担を抑えることができるのです。
6.生命保険の生前給付の活用
そして、生命保険特有の「保障」という機能も忘れてはいけません。
例えば、認知症や介護が必要になった場合に支払われる生命保険を契約していた場合、それらの生前給付金は非課税で受け取ることができます。
例えば、介護保障付の一時払いドル建終身保険を契約していたとしましょう。
米ドルの金利が高い昨今では契約から20年が経過した頃に保険金としてドル建てで1.8倍程度になっている契約もあります。
仮に1ドル=150円くらいのときに契約し、以前のような1ドル=110円に戻った時に保険金を受給したとしましょう。
この場合、支払った保険料に対して32%増えてくることになり、仮に1,000万円の保険料を払っているとしたら保険金は1,320万円として受け取ることができ、利益の320万円は非課税で受け取ることができます。
老後には生活資金のみでなく、認知症や介護が必要になった場合の費用の準備も大切です。
それらの費用も全て資産形成で賄っても良いですが、こういった生命保険を活用することで生前給付の非課税のメリットを使うことができます。
また、資産運用と保障をセットにしたような商品以外にも、掛捨てタイプの保険ですと少ない保険料で、将来給付金を受け取る場合には非課税で受け取ることができます。
医療・介護保険の保険料控除の対象にもなりますので、掛捨ての介護保険を所得が高い現役の頃に契約し、自分の将来に備えることで少し税負担も抑えながら将来それなりに高い確率で非課税で受け取る可能性のあるの保障を買うこともできます。
7.ふるさと納税の活用
そして、不動産の減価償却で節税し、そこから発生する税金をよりお得に抑える方法として、ふるさと納税があります。
所得が1,005万円程度の場合ですと、約25万円程度を上限にふるさと納税で税金の恩恵を受けることができます。
ふるさと納税は納税額の約30%程度の価値の返礼品を受けることができ、所得税、住民税が安くなるため、仮に25万円を納税しても、所得税と住民税が安くなった分で24万8000円分の税金を安くし、7万円程度の価値の返礼品に変えることができます。
温泉旅館の宿泊券や、各自治体限定で使えるPayPay商品券なども対象ですのでこちらの制度を活用してもよいでしょう。
8.資産管理法人の設立
更に資産管理法人を設立し、法人で資産運用するという方法もあります。
長期保有目的の証券の場合、配当などは課税の対象となりますが、資産の価格が上がっていても評価替えを行う必要が無く、売却するまで課税対象とはなりません。
そして、法人から個人に対し報酬も発生させることができるため、配当を報酬として受け取ることができます。
赤字でも年間7万円の法人住民税が発生したり、複雑な法人の確定申告の手間などや税理士費用は発生しますが、売却時まで課税されないという点は非常に大きなメリットですね。
そして、赤字が累積していけば欠損金の繰越控除でその後の年の利益と相殺することもでき、税金を抑えることが可能です。
このように資産を守る方法があり、税負担が大きくなっても年間数百万円単位で抑えることができ、手元に残せるお金は数年で1,000万円を超えてくる場合も多いものです。
NISAやiDeCoなどの制度を活用する以外にもできることはありますので、自分に合った方法を考え、それぞれの専門家と共同しながら仕組を創ることでこのようなことが可能です。
しかし、そのためには信頼できる専門家の存在と、有利な保険商品、不動産を提供してくれるプロの存在が必要です。
当オフィスではそんなネットワークを構築し、あなたの価値観や許容できるリスクに合った最適な方法を、あなたの立場でご提案いたします。
いわばあなたのブレーンとなり、「私があなたの立場なら・・・」という考え方で、特定の商品販売を目的とせずに、税金から可処分所得や資産を防衛する仕組みを考え、仕組を構築するまでのサポートをご提供しています。
今回ご紹介した方法についてもっと詳細を知りたい、他にどんな方法があるか知りたいという方は個別相談にて無料でお伝えしますので、税金から資産を守り上手に資産を残したい人はご連絡下さいね。
※解説した税制を活用したテクニックは2025年2月時点での税制を元にお伝えしています。今後税制改正等で変わる可能性もありますので、税制が変化した場合に状況に合わせて修正していく必要があります。